こんばんは、トレーナーの纐纈です!
野球をしていると、どうしても避けられないのが「デッドボール(死球)」です。
特に頭や首に硬式球が当たったときは、見た目に問題がなくても、脳にダメージが残っている可能性があります。
今回は、そうした場面で選手をどう守り、どう復帰まで導くかについて、最新の知見をもとにわかりやすく解説します。
今の課題:「大丈夫そう」が一番危ない
近年、「脳震盪(のうしんとう)」に対する意識は高まっています。
脳震盪とは、頭を打ったあとに起こる一時的な脳の機能障害で、頭痛やめまい、気持ち悪さなどが出ます。
ですが、特に中学生や高校生のような成長期の選手に対しては、評価や対応の仕方が統一されておらず、その場の判断で済まされてしまうケースも少なくありません。
「本人が大丈夫って言ってるから」とプレーを続けさせてしまうことは、選手の安全に大きなリスクを伴います。
まず覚えてほしいルール:「迷ったら外す・再確認」
- プレーを止める(Remove):頭に当たったら、症状がなくてもその場でプレーをやめさせてください。
- 再確認する(Re-evaluate):その後、時間をかけて状態を観察し、必要に応じて医療機関での確認を行います。
これは「少しでも脳震盪の疑いがあるなら、脳震盪として扱う」という世界的な原則です。
成長期の選手が頭にデッドボールを受けた場合の対応
① 試合中にすべきこと
- すぐにプレーを止める:たとえ「大丈夫」と言っても、その場から外してください。
- 危険な症状(レッドフラッグ)をチェック:例えば、
- 意識がはっきりしない
- 何度も吐く
- けいれん(体が勝手に震える)
- 手足のしびれや力が入らない
- 強い頭痛や、どんどん悪くなる痛み
これらがある場合はすぐに病院へ連れて行きましょう。
② 症状がなかった場合の対応
症状がなくても「安心してはいけません」。脳震盪の症状は、数時間後や翌日に出てくることもあるからです。
このため、受傷したその日はプレーに戻さず、少なくとも24時間は安静にしてください。できれば病院での確認をおすすめします。
③ 症状がある場合の対応
頭痛やめまい、気持ち悪さ、集中力の低下などがある場合は、脳震盪と考えて対応を始めます。
小学生には「Child SCAT6(チャイルド・スキャット・シックス)」、中学生以上には「SCAT6(スキャット・シックス)」というチェックシートのような評価ツールがあり、記憶・バランス・目の動きなどを総合的に確認できます。
これらは医療機関やトレーナーが使うツールですが、保護者の方でも覚えておくと参考になります。
回復までの流れと注意点
● 最初の48時間は「相対的な安静」
完全に暗い部屋でじっとする必要はありません。
ただし、スマホ、ゲーム、テレビなどで頭を使いすぎるのは控えめにし、静かに過ごしましょう。
● 2日後以降の軽い運動はOK
症状が出なければ、散歩や軽い自転車などから徐々に活動を再開していきます。
● 競技への復帰は「6段階」
以下の流れで、段階的に復帰していきます(各段階は1〜2日ずつ空けて進めます)。
- 日常生活に戻る(学校や家庭内の活動)
- ウォーキングや軽いジョギング
- 素振りや軽いキャッチボール
- ノックやティーバッティングなど複雑な動き
- 制限なしの練習参加
- 試合に復帰
小学生・中学生では各段階を最低48時間空けるのが理想とされています。
絶対に避けるべきこと
- 自己判断での復帰:「治った気がする」だけでプレーを再開するのは危険です。
- 鎮痛剤の使用:頭痛を薬でごまかすと、異常に気づくのが遅れることがあります。
- 当日中の練習・試合続行:受けた日は必ず休ませてください。
まとめ:「何もなかった」を確認するための時間が必要です
頭にボールが当たったとき、「大丈夫そう」に見えても、脳の中では変化が起きているかもしれません。
この時期の選手にとって、たった1回の判断ミスが将来に大きく影響することもあります。
保護者の方、指導者の方は、選手の気持ちを大切にしつつ、安全を最優先にした対応をお願いします。
そして何より、「安心して試合に戻れる」ことを確認してから復帰させることが、パフォーマンス向上にもつながります。
参考リンク(専門家向け)
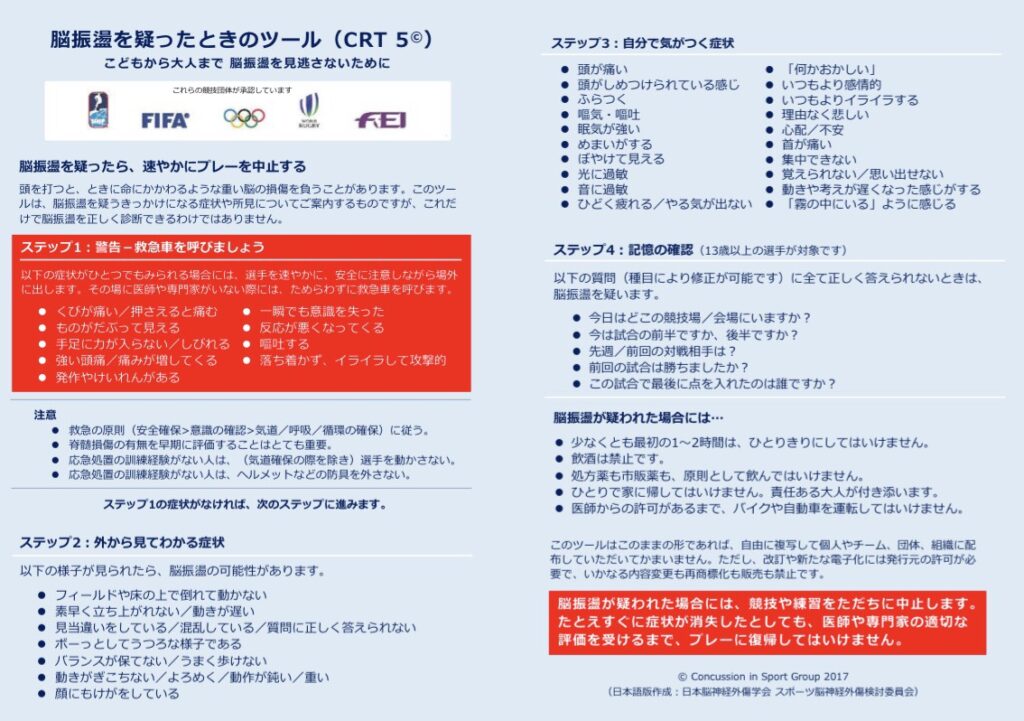



コメント